ゆらぎと家族・地域・市民社会 同志社大学文学部社会学科教授(2001年4月より) 立木茂雄
これまでの研究は大別すると3分野にまたがっている。それらは、1)家族研究(主として家族システム論からの接近)、2)市民社会論(主としてボランティア・NPOと行政の関係や市民性と家族システムとの関係について)、3)防災学(災害抵抗力・災害復元力・緊急対応・緊急支援・復興支援などの、いわゆる「ソフトな防災」について)である。
1)家族(家族システム)研究
実践的研究:1980年の関西学院大学における修士論文研究(武田建・立木茂雄『親と子の行動ケースワーク』ミネルヴァ書房, 1982)以来、トロント大学大学院博士課程を経て1986年に関西学院大学社会学部に赴任し、1990年代前半までの研究の主眼は家族システムに対する臨床実践(家族療法)にあった。1987年から1999年まで12年間にわたって神戸市児童相談所においてスーパーバイザー(指導・監督者)の立場で、不登校児童・生徒とその親を対象とした臨床的実践に関わってきた。これらの成果の大部分は『カウンセリングの成功と失敗』(創元社1991年、白石大介との共編著)にまとめられている。
家族を相互に作用しあう成員からなる一つのシステムとしてとらえた場合、家族療法における臨床は「家族システムのカオス性を増大する行為」と解釈できる。つまり不登校や家庭内暴力、拒食といった問題のある家族関係にあっては、成員間の相互作用の中に症状を維持させるフィードバック連鎖(問題維持連鎖)が発見される。それを断ち切ること(カオス反制御)が臨床の主眼点となる。
方法論的研究:夫婦・家族システムへの臨床的実践の効果を検討するためには客観的な夫婦・家族システムの測定尺度が求められる。そのためには普遍的に通用する理論と繰り返しの使用に耐えうる標準的な尺度の開発が不可欠である。そこで主として計量心理学の方法論に準拠しながら夫婦・家族システムの機能度を測定する用具(直接観察・評定・質問紙尺度など)の開発研究を進めてきた。1982年から1986年にわたるトロント大学大学院博士課程での研究テーマは夫婦相互作用過程の系列分析(sequential analysis)を高次マルコフ過程に対応するように拡張する試みであり、そのために双対尺度法(コレスポンデンス分析、林数量化理論Ⅱ・Ⅲ類)を利用するものであった。これは1994年にトロント大学に提出した博士請求論文にまとめられている。
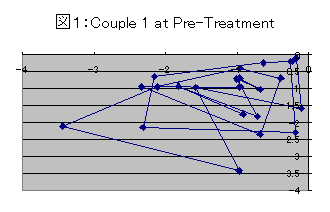
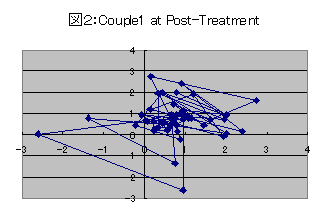 家族相互作用過程を計量化することによって時系列データが得られる。この時系列データを、事象tとt+1からなる相空間に描いて(first-return map)みた。図1が治療開始期、図2が治療終結期のデータである。治療開始期と治療終結期の家族相互作用過程ではあきらかに相違がある。治療開始期ではy=xの軸を中心として周期的な振動が観察されるが、治療終結期ではy=xの軸をはさんだ上下の振動は不安定で「ゆらぎ」の幅が大きい。試みに、この相互作用過程時系列データのカオス解析を行ってみた。データ数が極めて少ないために、あくまでも示唆的ものでしかないが、最大リアプノフ指数が治療開始期の0.295と比べて治療終結期では0.544と増加していた。
家族相互作用過程を計量化することによって時系列データが得られる。この時系列データを、事象tとt+1からなる相空間に描いて(first-return map)みた。図1が治療開始期、図2が治療終結期のデータである。治療開始期と治療終結期の家族相互作用過程ではあきらかに相違がある。治療開始期ではy=xの軸を中心として周期的な振動が観察されるが、治療終結期ではy=xの軸をはさんだ上下の振動は不安定で「ゆらぎ」の幅が大きい。試みに、この相互作用過程時系列データのカオス解析を行ってみた。データ数が極めて少ないために、あくまでも示唆的ものでしかないが、最大リアプノフ指数が治療開始期の0.295と比べて治療終結期では0.544と増加していた。
問題をかかえた家族では問題維持連鎖が見られ家族がもつダイナミクスは周期的であり「ゆらぎ」の程度が小さい。家族の臨床とは、そのシステムのカオス性を増大する行為であり、治療終結期では「ゆらぎ」の程度が大きくダイナミクスが豊かで多様であることが示されているように思う(立木茂雄「問題維持連鎖とシステム家族療法」合原一幸編『数理科学-生命とカオス特集』(サイエンス社)第381号60-66頁)。
簡便に利用できる用具の開発も1986年以来、大学院生・学部ゼミ生との共同研究の形で進めてきた。これまでに、オルソン,D.H.が提唱した家族システム円環モデル(Circumplex Model)に準拠した測定用具である家族システム臨床評価尺度(Clinical Rating Scale)、模擬的家族活動測定法(Simulated Family Activity Measurement)、そして現在第4版(小改訂3)にいたる日本社会版家族システム評価尺度(FACESKG, Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale)を開発してきた。なおFACESKGは、現在までのところ多特性・多方法行列実験を通じた構成概念妥当性の検討に実証的に耐えた唯一の家族システム評価尺度である。尺度開発の過程は、『家族システムの理論的・実証的研究』(1999年、川島書店刊)に詳述している。
実証的研究:家族システム評価尺度を利用した家族の実証調査研究としてこれまで取りくんで来たテーマには、登校ストレス・自我同一性の形成と失敗・アルコール依存症者の断酒継続・震災ストレスなどがある。これらの研究はどれも家族システム円環モデルに基づき、家族システム機能度を決定する2要因である「家族のきずな」・「家族のかじとり」と家族機能度の指標との関係性について検討するものであった。この場合、家族のきずな・かじとりをヨコ軸に、家族機能度の指標をタテ軸にとった場合には、両者の間に∩字型の関係が仮説化される。すなわち、どちらの次元でも中庸な水準にある場合に最も家族機能度が高まり、それを超えて高すぎても、あるいは逆に低すぎても家族機能度が下がるというものであった。これは円環モデルの基本的な仮説であるが、阪神大震災被災者に対する標本調査(1998年度)は、この∩字型仮説を実証するものであった。
2)市民社会論
1995年の阪神・淡路大震災時には、救援ボランティア組織の立ち上げと運営に携わった。この体験を契機としてボランティア・NPO活動に注目するようになった。救援ボランティアのマネジメント現場におけるアクションリサーチをもとに編集したのが『ボランティアと市民社会』(晃洋書房刊1997年初版、2001年増補版)である。同書では、ボランティア行為の社会科学的検討、市民社会論の中での位置づけ、フォーマル・インフォーマル組織連携の事例としてのボランティア・NPOと行政との協働関係、災害ボランティアのマネジメントなどのテーマについて検討している。また市民社会におけるボランティア行為の位置づけ、ボランティア・マネジメントやボランティア・マーケティングの実際については、1996年夏におけるカナダ・カルガリー市での取材をもとにしたDVDビデオ番組『カナダのボランティアリズム-公共性は市民が紡ぎだす』で、詳しく紹介している。
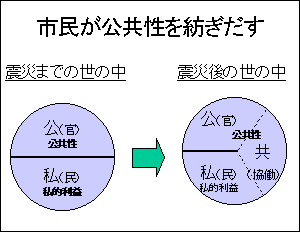
阪神大震災被災者に対する標本調査研究では、家族システムの変化と併せて社会生活上の市民性意識の変化についても調べている。そのために、市民一人ひとりの市民意識を探ることを目的とした市民性尺度(Civic-mindedness Scale)を独自に開発した。市民性尺度は「自律」と「連帯」というふたつの側面から市民性意識を測定するものである。この尺度は、1998年度の兵庫県調査と1999年度の神戸市1万人アンケート調査で用いられた。その結果、神戸・阪神間市民の間では、震災前後で市民性意識に統計的に意味のある違い(上昇)が生まれていることを実証した。
ボランティアもNPO活動も、「市民が公共性を紡ぎだす」活動である。市民や民間の団体も公共性を担って良いし、むしろ市民のつとめとして積極的に関わるべきだ。震災を経験した神戸・阪神間では、これが都市の新しい常識になろうとしている。図3は、世の中の見方がどのように変化したかを図式化したものである。世の中を、お正月の鏡もちにたとえるなら、それを真横一文字に切り取り、上半分を「公」、下半分を「私」とするのが震災までの世の中のとらえ方であった。「公共性=行政、私的利益の追求=民間」がその本質である。このような世界観では、公共性とは「他人ごと」の世界であり、「公」という「他人にまかせて」おけばよいものであった。しかし震災は、「公」でもなく、さりとて「私」でもない領域、すなわち「共」の領域が確実に存在することを私たちに教えた。「共」とは、市民が公共性を紡ぎ出す場であり、そこでは公共性が市民一人ひとりにとって「我がこと」と感じられる。震災後の混乱(カオスの縁)期には、公共性が公私を含めた多元的な主体によってになわれた。震災直後に出現したこの新しい現実は、私たちの世の中の見方を永続的に変えるだけの力を持っていたのだと思う。
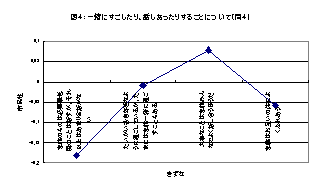
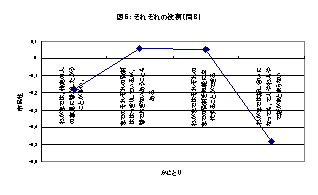 兵庫県調査に続いて1999年度には、兵庫県三田市において家族システムと市民性・社会的信頼・ジェンダーフリー意識などとの関係について調査した。その結果、家族のきずな(図4)・かじとり(図5)が中庸な場合に、市民性をはじめ社会的信頼やジェンダーフリー度が最も高まることを実証した。
兵庫県調査に続いて1999年度には、兵庫県三田市において家族システムと市民性・社会的信頼・ジェンダーフリー意識などとの関係について調査した。その結果、家族のきずな(図4)・かじとり(図5)が中庸な場合に、市民性をはじめ社会的信頼やジェンダーフリー度が最も高まることを実証した。
健康な家族では「ゆらぎ」の程度が大きくダイナミクスが豊かで多様である。そのような家族システムが、市民社会をささえる「自律」や「連帯」意識の発酵装置であることが示されているように思う。
現在は、この調査結果をもとに三田市内の女性自身が男女共同参画社会づくりの主体として施策策定の当初の段階から参画を行えるようにするためのワークショップを開催して行動計画の中に反映させる実践を行っている。
家族システムの実証調査研究における家族システムの内包的(臨床的)研究および外延的(市民社会との関わりを視野に入れた)研究については『家族社会学の分析視覚』(野々山久也・清水浩昭編著 近刊)に収められる「家族システム論」の章で、概要を説明している。今後の研究方向としては、1)家族研究と2)市民社会研究をクロスオーバーする領域での研究に力を入れて行きたいと考えている。そのような方向の具体例には、”Family system adjustment and adaptive reconstruction of social reality among the 1995 earthquake survivors”(共著者 立木茂雄・林春男 International Journal of Japanese Sociology, 9, 81-110)などがある。
3)防災学
震災救援ボランティア活動の体験、被災者復興支援会議メンバーとして被災者の自立支援を目的とした被災者・支援者へのアウトリーチとアドボカシー活動、またH9年からH11年度の文部省科学研究費特定領域研究(A)(I)「「都市直下地震」、またH11年度からの文部省科学研究費特定領域研究(B)(2)「日米共同研究による都市地震災害の軽減」への研究協力者としての参加を通じて、いわゆるソフト防災の分野における研究を継続する一方で、コンサルテーションや提言・提案などの実践も併せて行ってきた。
たとえば、神戸市民や西宮市民を対象とした被災市民参加型の草の根ワークショップによる生活再建構造の概念化や生活再建支援施策の構築などは、神戸市の震災復興計画推進プログラムのなかに活かされた。また、21世紀最初の1・17から始まった神戸市の復興記念事業「ひと・まち・みらい」は、人と人とのつながりを豊かにすることを通じて生活を再建させるための壮大な社会実験だが、神戸がより開かれたまちになるための応援団としても活動を行ってきた。
復興記念事業では、「この指とまれ」式の市民提案を積極的に事業化するとともに、事務局への市民参画、市民による企画・実践事業の推進、地域イベントを重視している。資金面でも、市民側が汗を流して自己調達した資金30億円、その同額を行政がマッチング・ファンドとして協働している。どれをとってみても、株式会社神戸市と揶揄された都市経営手法とは180度異なる創意・工夫で市民・企業・行政の協働が実験されている。
一握りの人間の頭だけで計画するのではなく、「する・見る・考える」という自律的なふりかえりを一人ひとりがくり返す。やがて、つながりを通してこころがふるえあう。「する・見る・考える」の循環はさらに広がり、いつのまにか予想もつかないほど大きな渦となる。神戸からの感謝の手紙も、「希望の灯り」市民ランナーも、「150万本のひまわり」運動も、そもそもはたった一人のこころのふるえから始まった。このようなかたちで、多くのこころがつながり復興が創発されていけばよい、と願っている。




